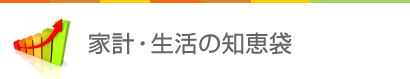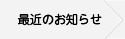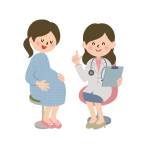お仕事ママ必読!産休・育休中にもらえる3つのお金とは
公開日:
:
社会保障や公的保険
産休・育休制度が使えることは知っていても、長期に渡って休むとなると、気になるのはやはりお金のことではないでしょうか。
これから新しい家族が増え、支出も増えると心配しているママのみなさんも多いと思います。
そこで今回は、産休・育休中にもらえる3つのお金と支給のタイミングについてご紹介していきたいと思います。充実した社会保障を知ることで、きっと安心して出産、育休に備えることができると考えます。
なお、本記事は、平成28年3月現在の各種法令に基づいて執筆掲載しておりますので、法改正による掲載内容の相違がある可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
1 出産育児一時金
出産1人につき42万円支給
出産育児一時金は出産費用の軽減を図るため、健康保険の被保険者が出産した場合、子ども1人につき42万円が支給されます。
ここでいう「被保険者」とは、給与や賞与から健康保険料が天引きされている人を指しています。また、双子の場合は「多胎妊娠」といって倍額の84万円が支給されますので合わせて知っておきたいポイントです。
出産育児一時金が支給される対象は、妊娠4ヶ月以上の場合で、流産や死産の場合にも支給されます。
また、被扶養者(専業主婦や娘など)が出産した場合は、被保険者(この例では夫)に家族出産育児一時金が支払われます。
余談ですが、出産育児一時金も家族出産育児一時金も支給内容は同じで名称が異なっているだけの違いになります。
会社を辞めて健康保険に入っていない人は?
退職などで健康保険の被保険者の資格を喪失する場合は、その喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産した時は、出産育児一時金が支給されます。
わかりやすく例えますと、健康保険料が給与などから天引きされている女性が授かり婚や出産・子育てのために1年以上働いた会社を退職したとします。その後、半年以内に子どもを出産した場合、健康保険に加入していないので本来ならば出産育児一時金の支給対象にはならないのですが、特別に支給しますといったイメージです。
給付の手続きと支給のタイミング
出産育児一時金は、平成21年10月1日から健康保険から医療機関に直接支払われることになり、これを「直接支払制度」といいます。
実際、出産にかかった費用が42万円を超える場合は、本人が医療機関に差額を支払い、42万円未満であった場合は、後日残りの額を医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に請求することになります。
医療機関で直接支払制度を利用する旨を確認され、健康保険証の提示が必要になりますが、後の手続きは医療機関が実施してくれます。以前は、本人が全額を一旦負担した後に支給されていました。
医療機関によってはおおよその入院費用を明示しているところもありますが、備えるお金の目安は以下の通りです。
入院費用-出産育児一時金(42万円)の差額分+α
直接支払制度によってあらかじめ備えておくお金の金額もだいぶ変わるため、まとまったお金を必ずしも用意しておかなくてもよいこともあり、もしかしたら少し不安が軽くなることもできたのではないでしょうか。
2 出産手当金
出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休み、その間給与が支払われないとき、産前6週間(多児妊娠の場合は14週間)および出産の日後8週間、原則として1日につき標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給されます。
産前産後休業中で無給期間の生活をサポートする目的で、会社が加入している健康保険から支給されます。
出産手当金の支給額=標準報酬日額×3分の2×産前産後休暇日数
ただし、産前産後休業の期間であっても、会社から給与が支払われた場合は、出産手当金の額からその額が差し引かれます。
また、産前・産後休暇は出産予定日が基準になりますので、出産が予定日より早まったり遅れたりすると支給される額は変わってきます。
給付の手続きと支給のタイミング
出産手当金の手続きは、会社が実施してくれる場合が多いと思います。
まず職場の担当部署を確認し、申請用紙(健康保険出産手当金支給申請書)をもらいます。担当医に記入してもらう欄がありますので、産休前に準備し、入院時に持参できるようにしておきましょう。
出産後、医師に必要事項を記入してもらうほか、自身も不備なく書類に記入し申請用紙を提出します。書類の提出先は、会社が手続きを行う場合は会社へ、自分で提出する場合は加入先の健康保険事務所へ提出します。
出産手当金は、お金が振り込まれるまでの日数が少し長いといった特徴があります。
そのため、早急にお金を必要としている人に対しては、希望により産前・産後と分割して請求することも可能な仕組みになっています。
提出した書類に不備がなければ、申請後早ければ約2週間程度で出産手当金が振り込まれますが、いずれにしましても出産してすぐにもらえるお金ではないですので注意が必要といえます。
なお、産前産後休業期間終了後にまとめて請求する場合、申請は産後休暇終了後になりますので、支給は早くても出産後2か月後~遅ければ4か月後ということも考えられます。おおまかであったとしても、やはり出産前の資金計画は大切だといえるでしょう。
3 育児休業給付金
育児休業給付金は、産後休暇が終了し育児休業期間中に支給されるお金で、赤ちゃんが1歳になるまでの期間(特別な場合は1歳6か月まで)に本人が加入している雇用保険から経済的な支援として支給されます。
育児休業給付金の金額は、育児休業開始日から180日目までは休業前賃金の67%、育児休業開始から181日目以降は休業前賃金の50%となります。
この休業前賃金は、ハローワークが育児休業開始前の給与などを基礎として計算し決定する仕組みとなっており、育児休業給付金の支給可否と合わせて金額を確認しておくことをおすすめします。
給付の手続きと支給のタイミング
ハローワークに問い合わせることで育児休業給付金を受け取れる資格があるかないかを調べてもらうことができますが、参考までに支給対象を下記へ紹介します。
・1歳に満たない子(保育園に入所できないなどの場合は1歳6か月まで)を養育するための育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者であること。
・育児休業を開始した日の前2年間に、雇用保険に加入し賃金を受けた日が11日以上ある月が通算12か月以上あること
支給申請の手続きは基本的に本人に代わって事業主が行います。そのため事業主の指示に従って適切な手続きを行うことが育児休業給付金を早く受け取るためのキーポイントになります。
育児・出産給付金のまとめ
今回は、産休・育休中にもらえる3つのお金を紹介しました。
社会保障制度が充実していることはありがたいと、この時ばかりは身に染みて感じることができるママのみなさんも多いことでしょう。
また、お休み中でも意外とお金がもらえると安心した方も多かったのではないでしょうか。産休・育休中にもらえるお金は支給まで時間がかかることも多いため支給のタイミングを知って、賢く備えたいものです。
PC用
関連記事
-

-
海外に行くなら知っておきたい海外療養費制度の活用
国民皆保険と海外療養費制度 私たち日本人はそれぞれ1人1枚保険証を持っています。いわゆる「国民皆保
-

-
医療費増加と今後の懸念
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2014年度の収支が前年度に比べて約2倍の3726億円の黒字になると
-

-
【FPが教える】家計管理が苦手な人でもお金を増やせる投資・節約法ランキング
投資は難しそう、節約は苦手という声をよく聞きますが、ほとんどの場合知らないだけです。人は知らないこと
-
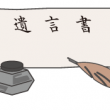
-
永久保存版!子育て世帯が知っておくべき2つの遺族年金と仕組み
多くの皆さんが「遺族年金」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。 しかしながら、遺族
-

-
妊娠~出産にかかる費用が安くなる公的保険と不妊治療助成制度をまとめました。
妊娠していることがわかると、大きな喜びを感じる一方で、今後のお金の面でさまざまな不安を抱えるようにな
- PREV
- リバースモーゲージの基本と活用方法
- NEXT
- 海外旅行保険が値上げの見通し