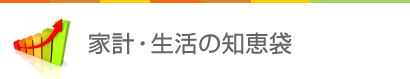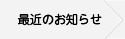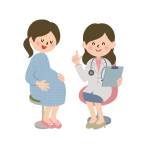【確定拠出年金の攻略マニュアル】 始め方から利益を出す鉄則まで
 (この記事はかな~り長いので、少し下に表示されている目次もご利用ください。
(この記事はかな~り長いので、少し下に表示されている目次もご利用ください。
先に要点を見たい方は、ここを押してもらえれば「まとめ」コーナーに移動します。)
確定拠出年金(401k)の法律の改正が成立したことを受けて、確定拠出年金に大きな注目が集まっています。中には、「確定拠出年金って何?」「確定拠出年金という言葉だけは聞いたことがある。」といった人もきっと多くおられることでしょう。
確定拠出年金とは、簡単に説明すると「老後の生活資金」のことで、国民年金のように納付義務があるものではなく、自主的に老後の生活資金を貯める方法の1つです。
ここだけ聞くと、「毎月少しずつお金を積み立てて貯めていればそれでいいのでは?」と思うかもしれません。
確かにそれも老後資金を貯めるための方法の1つですが、確定拠出年金には貯金には無いメリットが多くあります。
この記事では、確定拠出年金の基本的な部分から、お金を増やすポイントや活用方法までを幅広く、そして詳しく解説していきます。
ただ「確定拠出年金の攻略マニュアル」と題していることもあってかなりの長文です。
時間があまりない方には以下の目次から気になるポイントを読んでいただくのも良いですし、印刷してじっくり読んでいただいても嬉しいです。
読み終えた後には、きっと多くの皆さんが確定拠出年金の加入を検討しているでしょう。資産設計のお役に立てていただければと思います。
1.そもそも確定拠出年金(401k)とは何なのか
確定拠出年金(401k)とは、「会社や自分が拠出(積み立てた)お金を元手とし、自分で老後資産を作るための方法」です。
平成28年度における国民年金の支給金額は、20歳から60歳までの40年間をすべて納付した場合で、「年額780,100円」となっておりますが、この年金額が将来において必ずしも維持されるものではありません。
今後、もらえる年金額が今よりも少なくなる可能性や年金を受け取れる年齢が引き上げられる可能性を考慮すると、確定拠出年金のように自助努力によって資産形成できる「老後の自分年金」を作っていくことが重要になってきます。
確定拠出年金のメリットは、後程、詳しく紹介していきますが、まずは基本的な部分から順を追って解説します。
1-1.確定拠出年金は大きく2つに分けられる
確定拠出年金は、
・企業型確定拠出年金(企業型401k)
・個人型確定拠出年金(個人型401k)
の2つに分けることができます。
これら2つの確定拠出年金はまったくと言ってよいほど仕組みが異なっていて、まずはこの2つの違いを以下の表へまとめて解説します。
企業型と個人型の違い
| 企業型 | 個人型 | |
|---|---|---|
| 利用の目的 | 退職金 | 老後資金 |
| 拠出する人 | 法人(一部、個人可能) | 個人 |
| 運用する金融商品 | 会社が決めた運営管理機関の商品から選択 | 最初に自分で運営管理機関を選んで自由に選択可能 |
企業型は、会社の退職金制度と考えて差し支えありません。そのため、すべての会社で企業型があるのではなく、勤務している会社が確定拠出年金制度を採用している場合に加入することができる仕組みになっています。
自分の会社が、確定拠出年金の企業型に加入しているか分からない場合は、勤務先の総務担当者や経理担当者に聞いてみるのが確実でしょう。仮に自分が勤めている会社で確定拠出年金制度を採用していない場合は、個人型に加入することになります。
なお、表中にある「運営管理機関」とは、銀行等の金融機関や証券会社等のことを指します。
たとえば、確定拠出年金の個人型に加入する場合には、はじめに運営管理機関を選びます。すべての金融機関で確定拠出年金を取り扱っている訳ではない点や、取り扱う金融商品や手数料等も異なる特徴がありますので、運営管理機関選びで失敗するのは絶対に避けなければなりません。
1-2.運営管理機関はどこにしたら良いの?という人へのお勧め。
筆者としてオススメしたいのは、「運営管理手数料が無料」という圧倒的コストパフォーマンスの松井証券です。
私もここの証券会社で確定拠出年金を運用しており、コストの安さと商品数にはかなり満足しています。
公式HP 松井証券での確定拠出年金を始める方はこちら
積立て状況や損益状況をインターネットでいつでも確認ができる点も素晴らしいです。
また参考までに、特定非営利活動法人「確定拠出年金教育協会」が運営しているサイトリンクも紹介します。
このサイトでは、確定拠出年金の個人型を一覧で比較できるだけでなく、運営管理機関が取り扱っている金融商品の種類や手数料など知りたい情報をまとめて比較しながら知ることが可能です。初めて確定拠出年金をやってみようと考えている人にとっては便利なツールです。
参考ツール 個人型確定拠出年金ナビ
2.確定拠出年金のメリット
確定拠出年金のメリットは様々ありますが、その中でも最大のメリットは「老後の資金を貯めながら税金の軽減ができる」ことです。
さらにこのメリットを受けれるのは1回だけでなく、
① 拠出時(積み立てている間)
② 運用中
③ 受取時(60歳以降)
と一連のすべての流れにおいて節税効果が認められます。
ここでは、これらのメリットをそれぞれ解説していきます。
2-1.拠出時(積み立てている間)の節税メリットについて
確定拠出年金には、「加入できるのは60歳まで」といったルールがあります。もし25歳の時に確定拠出年金に加入したとすると、最大で25歳から60歳までの35年間、加入できることになります。
たとえば、年収400万円の会社員や公務員が確定拠出年金に加入して1ヶ月12,000円を拠出したと仮定します。この場合、1年間で拠出した144,000円(12,000円×12ヶ月)は、「小規模企業共済等掛金控除」として所得税及び住民税の全額所得控除の対象となり、1年間の所得税と住民税を合わせた節税効果を計算すると、毎年およそ30,000円の節約ができていることになります。
これはほんの一例ですが、年収が高い人や扶養人数が多い人などの場合はさらに節税効果が高くなります。
2-2.運用中の節税メリットについて
確定拠出年金の運用中のメリットは、何と言っても「運用益に対する非課税」です。
例えば、確定拠出年金に加入して元本10万円を投資信託に拠出したと仮定します。その結果、投資が成功し初年度2万円の利益が発生した場合、本来は発生した2万円の利益に対して「20.315%」の税金4,063円が徴収されることになっています。
つまり、実質的な利益は15,937円となってしまうのです。
しかし、確定拠出年金で運用した投資信託の利益は「非課税扱い」とされているので、2万円の利益に対して税金が徴収されることはありません。
この場合における翌年度の元本は、当初の10万円に利益を合算した12万円となります。元本が多くなれば、その分、利益も大きくなることから結果として「複利効果」が大きくなり、投資した確定拠出年金の資産が増えやすくなります。
もちろん確定拠出年金の運用商品によっては当初の元本10万円よりも少なくなるリスクはありますが、通常の金融商品に比べたら「大きな運用利益を得ても税金を払わなくても良い」というのは圧倒的に大きなメリットと言えるでしょう。
2-3.受取時の節税メリットについて
確定拠出年金は、原則として60歳からお金を受け取ることが可能ですが、
・受取方法は一括でお金を受け取る「一時金」、
・分割でお金を受け取る「年金」、
・「一時金と年金の併用」
の3つの方法があります。
そして、これらの方法でお金を受け取る際において、所得税法で認められている「退職所得控除額」や「公的年金等控除額」といった控除額の適用が可能になります。
つまり、受け取るお金などの金額や条件によっては所得税や住民税を徴収されなくて済むというメリットがあります。
以下では、確定拠出年金を一括で受け取った場合のイメージと分割で受け取った場合のイメージを解説していきます。
確定拠出年金を一括(一時金)で受け取ったときにかかる税金
確定拠出年金を一括(一時金)で受け取った場合、その受け取ったお金は「退職所得」として所得税および住民税の課税の対象となります。
ただし、退職金の性質上、税金の計算におきましては、他の収入よりも優遇された取り扱いとなっています。
ここでは具体的な例をあげて確定拠出年金を一括で受け取った場合の税金のイメージについて紹介します。
確定拠出年金を一括で受け取った場合に税金がかかるか、かからないかを調べるためには、「退職所得控除額」を計算する必要があります。計算式は以下の通りです。
なお、ここでは「勤続年数」ではなく確定拠出年金に加入した「加入年数」に置き換えて解説します。
| 加入年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×加入年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(加入年数-20年) |
たとえば、29歳の時に初めて確定拠出年金に加入したと仮定し、60歳になるまでの「30年6ヶ月」が加入期間だったとします。この場合における退職所得控除額は、以下の様に計算されます。
・ 6ヶ月等の半端は、1年に切り上げて計算するため「加入期間は31年」となる
・ 加入年数「20年超」のため「800万円+70万円×(加入年数-20年)」にあてはめる
よって、800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円となります。つまり、60歳で確定拠出年金を一括で受け取る場合、1,570万円以下であれば所得税も住民税も納めなくともよいとなるのです。
ただし注意点として、仮に60歳で定年退職を迎え、勤務先からも退職金が支給される場合には、合算金額によっては必ずしも税金がかからないといった保証はありませんので、勤め先の退職金と確定拠出年金を一時金でもらった場合の合わせた金額がいくらになるのかをあらかじめ確認しておく必要があります。
金額が大きいだけに安易な判断は、大きな税負担となる可能性も否めませんので、場合によっては税理士といった専門家に相談するのも良いでしょう。
確定拠出年金を分割(年金)で受け取ったときにかかる税金
一方、確定拠出年金を分割(年金)で受け取った場合において、その受け取ったお金は「雑所得」として所得税および住民税の課税の対象となります。
こちらの場合でも退職所得控除額と同様に、「公的年金等控除額」があります。
確定拠出年金を分割で受け取った場合に税金がかかるか、かからないかを調べるためには、「公的年金等控除額」を計算する必要があります。
確定拠出年金は、60歳から分割で受け取ることも可能ですが、公的年金等控除額の計算において「65歳未満」と「65歳以上」の計算式には違いがありますので注意が必要です。ここでは、国税庁ホームページで公開している「公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)」を基に解説していきます。
| 年齢 | ①公的年金等収入金額の合計額 | ②割合 | ③控除額 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | |||
| 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額が0円となります | |||
| 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
| 年齢 | ①公的年金等収入金額の合計額 | ②割合 | ③控除額 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | |||
| 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額が0円となります | |||
| 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
出典 国税庁ホームページ 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法より引用
たとえば、60歳になって確定拠出年金を分割(年金)で受け取ることにしたと仮定します。この時、1年間に確定拠出年金から受け取れる年金額が100万円であった場合における雑所得は、以下の計算式にあてはめて計算することが可能です。
公的年金等に係る雑所得の金額=①×②-③
60歳ですので、上記計算式にあてはめると雑所得の金額は以下の様になります。
1,000,000円×100%-700,000円=300,000円
仮に60歳で定年退職を迎え、同じ勤務先で嘱託再雇用という形式で働かない場合におきましては、所得税や住民税がかかる心配はないと予測されます。
一方で、今までの給料が下がったとしても嘱託再雇用で定年退職後も働き続けた場合には、勤務先からの給与所得と合算して計算することになるため、場合によっては無駄な税負担を強いられてしまう恐れがあります。
定年退職後のライフプランをどのようにするのかによって、確定拠出年金の受取方法を工夫する必要があると言えます。
意外な落とし穴。ちりも積もれば山となる「振込手数料」
確定拠出年金の受け取りを分割で行う場合は、銀行口座に振り込まれる際の「振込手数料」について考えておく必要があります。
多くの金融機関では、振り込む際の手数料について「400円+消費税」を振り込む度に徴収しています。年換算しますと5,184円が余計なコストとしてかかっていることになり、10年確定年金だと51,840円、20年確定年金だと103,680円と破格な金額になります。
せっかく長い間運用してきた儲けが振込手数料で徴収されるのはもったいないですね。
ただ、このように書くと「確定拠出年金は分割(年金)で受け取るのは、税金負担も多いし、振込手数料も高くなるから良くない」と思われるかもしれませんが、これはケースバイケースです。
大切なことはライフプランを考慮しながら最適な受け取り方法を選択するということなので、つまりお金に困らない円滑な流れ=キャッシュフローを考えることが最も重要なのです。
2-4.確定拠出年金の節税以外のメリット
確定拠出年金に加入する最大のメリットとして「節税効果」について解説しましたが、本項ではそれ以外のメリットについて2つ解説していきます。
運用手数料が安い
こちらのメリットは、後程解説する確定拠出年金の運用方法について「投資信託」を選んだ場合におけるものになりますが、証券会社や銀行等で売られている投資信託と確定拠出年金専用の投資信託では、同じ投資信託であったとしても、その運用手数料に2倍や3倍の開きがあると言っても過言ではありません。
投資信託の運用手数料は、いわばコストにあたるため、仮に投資信託で儲け(リターン)が生じたとしても、運用手数料であるコストを差し引いた時、その分の儲けが少なくなります。
1回だけならまだしも、確定拠出年金のように長期間で運用するものであれば、運用手数料の差は、将来受け取る年金額に大きな影響を及ぼします。
よって、もしあなたが投資信託をするのであれば、一般の投資信託よりも、確定拠出年金を利用した投資信託の方がより多くの儲け(リターン)の得られる可能性が高くなります。
また、運営管理機関(金融機関)によって運用手数料や信託報酬などのコスト負担が異なりますので、コストができる限り安い運営管理機関を選ぶことが大切になります。
オススメしたいのは、「口座管理手数料が無料」という圧倒的コストパフォーマンスの松井証券です。
私もここの証券会社で確定拠出年金を運用しており、コストの安さと商品数にはかなり満足しています。
公式HP 松井証券での確定拠出年金を始める方はこちら
積立て状況や損益状況をインターネットでいつでも確認ができる点も素晴らしいです。
勤務先が倒産しても影響がない
定年を迎えることで多くの人がもらえる退職金ですが、この退職金は賞与と同じように必ずしももらえるものとは限らないお金です。万が一、会社が業績悪化の末、倒産した場合は、本来支給されるべき退職金が出ないことも十分考えられます。
退職金は、人それぞれ使い道が異なりますが、中には公的年金と同様に老後の生活資金の一部として考えている人も多いと思います。これが出ないとなっては、大変では済まされない事態が起こってしまいます。
一方で、確定拠出年金に加入している法人(確定拠出年金企業型)の場合は、万が一会社が倒産したとしても退職金が支給されないといった最悪の事態は避けられるメリットがあります。
この理由は、確定拠出年金を始める際に、確定拠出年金用の個人口座を作成して、その口座に毎月積み立てていく仕組みになっているため、勤めている会社と本人の口座は分離独立していることになります。したがって、勤めている会社が倒産した場合や業績が悪化した場合において、将来受け取る確定拠出年金額に影響を与える不都合が問われることはありません。
また、勤め先で確定拠出年金制度を採用していなかったとしても、自身で確定拠出年金個人型に加入していることで、老後の生活資金だけでなく退職金の代わりとなる資金を積み立てておくことができるメリットもあります。
3.確定拠出年金のデメリット
何事にも良い点、悪い点は付き物ですが、確定拠出年金についても同様のことがあてはまります。ここでは、確定拠出年金のデメリットについて解説していきます。
3-1.原則として60歳までお金を引き出すことができない
確定拠出年金の拠出したお金は、原則として60歳まで引き出すことはできません。したがって、急にお金が必要になった時などに、普通預金のように引き出したり、投資信託の様に換金して現金化するといった資金の流動性に欠けるデメリットがあります。
確定拠出年金に加入する時は、余裕のある資金の範囲内で行うことが求められます。
3-2.「自動移換」のデメリットが多すぎる
多くの方に共通して言えることだと思いますが、確定拠出年金の加入中において、様々な理由から勤務先を離職したり退職したりすることが時にあると思います。
このような場合、企業型の確定拠出年金に加入していた場合は、事務担当者が必要な手続きを取ってくれる可能性もありますが、基本的には、「決まった期限以内に自分で手続きをすること」が求められます。
いわゆる確定拠出年金の「正しい手続き」をしなかった場合には、今まで掛けてきた確定拠出年金が自動的に移換されることになります。これを「自動移換」と言いますが、マイナスな面が多々あります。
主な自動移換のデメリット・注意点は、以下の5つです。
「自動移換」の注意点1.今までの運用資産がすべて現金化されてしまう
加入していた確定拠出年金が自動移換されてしまうと、今までの運用資産がすべて現金化されてしまいます。
別にたいしたことがないと思われる人も多いのかもしれませんが、たとえば、この現金化された資産を60歳まで開けることのできない貸金庫に勝手に入れられてしまってはどうでしょう?お金を引き出すことができず、ただ60歳まで貸金庫の手数料を支払っているのを想像してみて下さい。明らかに無駄ではないでしょうか?
自動移換は、このような状態を作り出していることになります。
「自動移換」の注意点2.継続した手数料がかかる
加入していた確定拠出年金が自動移換されてしまうと、様々な手数料がかかることになります。
手数料金額は今後変更になる可能性もありますが、平成28年6月現在では以下のような手数料がかかります。
・ 特定運営管理機関手数料 3,240円
・ 国民年金基金連合会手数料 1,029円
・ 管理手数料 毎月51円
・ 移換手数料 1,080円
・ 個人型への移換手数料 2,777円
上記すべての手数料が毎月かかる訳ではありませんが、自動移換によって無駄なお金を手数料として支払う必要性が生じてしまいます。
「自動移換」の注意点3.自動移換中は全く運用ができない
加入していた確定拠出年金が自動移換されてしまうと、その期間中は全く運用ができないことになります。
つまり、今までの運用資産がすべて現金化された状態で国民年金基金連合会が長期保管しているだけになるため、確定拠出年金の目的である老後の資金が貯まることなく、ただ手数料を支払っているだけとなります。
「自動移換」の注意点4.自動移換中は加入期間とみなされることはない
加入していた確定拠出年金が自動移換されてしまうと、その期間中は確定拠出年金に加入している期間とはみなされません。
| 確定拠出年金の加入期間 (60歳到達時) |
確定拠出年金の受取開始可能年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳から70歳の間で任意で受取可能 |
| 8年以上~10年未満 | 61歳から受取可能 |
| 6年以上~8年未満 | 62歳から受取可能 |
| 4年以上~6年未満 | 63歳から受取可能 |
| 2年以上~4年未満 | 64歳から受取可能 |
| 1ヶ月以上~2年未満 | 65歳から受取可能 |
定年退職年齢が60歳である企業がまだまだ多い中で、確定拠出年金の最大の醍醐味は、定年退職した60歳からお金を受け取れるところにあると言えます。
公的年金は、原則として65歳から支給されることになりますので、いわば「空白の5年間」を埋め合わせてくれる強みが確定拠出年金にはあります。
ところが自動移換中におきましては、上記表の確定拠出年金の加入期間に含まれないため、場合によっては60歳から確定拠出年金を受け取ることができないといった弊害が起こり得る可能性があります。
「自動移換」の注意点5.自動移換状態では確定拠出年金の給付が受けられない
加入していた確定拠出年金が自動移換されてしまうと、60歳など本来ならば受け取りが可能な年齢に達していた場合でも給付が受けられないことになります。いずれにしましても手数料を支払って自動移換の状態ではないことにしなければならないため、結果として時間とお金がかかります。
ここまで来ると踏んだり蹴ったりで「自動移換だけは絶対に避けなければならない」とさすがに感じるのではないでしょうか?
4.確定拠出年金で選べる運用商品の種類
確定拠出年金で選べる運用商品は、「預金および保険」「国内債券」「国内株式」「外国債券」「外国株式」の5つに大別されます。
| 運用商品 | 特徴 |
|---|---|
| 預金および保険 | 元本が確保されており安全に運用することができるが、利回りは低い |
| 国内債券 | リスクもリターンも小さい |
| 国内株式 | リスクもリターンも大きい |
| 外国債券 | 安全性は高いが為替変動の影響がある |
| 外国株式 | 株価と為替の影響がある |
この内、「預金および保険」は「元本確保型」と呼ばれていて、確定拠出年金の運用で絶対に損を出したくないと考えている人は、「元本確保型」に加入すればよいことになります。
確定拠出年金は、このように自分で運用方法を選択し、損をするリスクとお金が増えるリターンの関係を踏まえながら、将来受け取る金額の増減は自己責任で決定していく仕組みになっています。
また、選べるのは1つの運用商品だけでなく複数商品を選ぶことができ、すべての運用商品を組み合わせて自由に運用することができるのが、確定拠出年金の醍醐味とも言えます。
配分変更のイメージ例
現在の運用状況 1ヶ月の掛金 2万円
定期預金 10,000円(50%)
国内株式 5,000円(25%)
外国株式 5,000円(25%)
↓↓↓
配分変更後の運用状況 1ヶ月の掛金 2万円
国内株式 5,000円(25%)
外国株式 15,000円(75%)
上記の配分変更は、リスクを取ってでも多くのリターンを得ようとする意図を感じ取ることができますね。この理由は、元本確保型である定期預金分のお金を外国株式に回しているためです。
このように、自分の考えや意図で自由に運用商品に投資する配分を変更することができます。
5.確定拠出年金でお金を増やしていくには。上手な運用の仕方。
人の性格は、皆異なっている特徴がありますので、確定拠出年金における自分年金作りの方法につきましても自分に合った運用方法が様々存在します。
たとえば、「大きく増やしたい」「損をしたくない」などいわゆる「リスク許容度」が人によって異なっているからこそ、万人に対して「この運用方法がおすすめ!」といったアドバイスは困難です。
ですが、あえて確定拠出年金を有効かつ賢く利用するのであれば、確定拠出年金で利益を出すためには次の3つが重要な鉄則になります。
鉄則1.無理のない拠出できる範囲(余裕資金)で、大きく運用する(リスクを取りに行く)!
鉄則2.コスト削減のため、運営管理機関の手数料は、安いものを選ぶ!
鉄則3.始めるのは思い立ったらすぐに!時間を味方につけて資産を増やす!
確定拠出年金は、運用中の税負担がないことから投資をして儲けた利益に対して税負担が必要なく、複利効果が期待できます。
これは「雪だるま式」とも呼ばれ、お金が雪だるまの様にどんどん積み重なって貯まっていくことから、そのように呼ばれています。これを20年や30年といった長期で運用することは、確定拠出年金に投じたお金が大きく増える期待を持てることになります。
これは他の金融商品にはない大きなメリットです。
だからこそ、余裕資金で拠出をしたらリスクをある程度以上はかけ、中~大のリターンを取りに行ったほうが良いと言えるでしょう(鉄則1)。
どの商品がプラスになるかはそのときの経済情勢・市場情勢によるので一概には言えませんが、確定拠出年金の妙味を実感できるはずです。
そして、この増えたお金を少しでも減らさない様にするためには、運営管理機関に支払う手数料が安いものを選ばなければなりません(鉄則2)。
せっかく税金がかからない利益を出すことができていても、手数料が高くついてしまっては意味がありません。
個人的には
・選択できる商品が多い
・手数料が最安値
となっている松井証券が一番オススメです。
そして、最後には「時間」を味方につけましょう(鉄則3)。
確定拠出年金に加入できるのは60歳という制限があるのですから、少しでも早くにスタートさせ、資産が増えていく仕組みを持ち続けることが重要です。
この単純明快な3つの鉄則を守るだけでも確定拠出年金で多くのお金を残すことができる可能性が大きく上がります。
確定拠出年金に加入した後は、定期的に送られてくる運用結果を見たり、インターネットで運用結果を確認しながら資産配分や投資配分を調整していくと更に大きくお金を増やせる可能性が広がることでしょう。
6.確定拠出年金の加入方法と流れ
ここでは、確定拠出年金の加入方法と流れについて解説していきます。
6-1.まずは「加入資格」があるか、ないかを確認しましょう
まずは確定拠出年金の加入資格があるか、ないかを必ず確認しておく必要があります。
そもそも加入資格が無ければ、いくら確定拠出年金の運用方法などを調べてその内容等を知っていたとしても無駄になってしまうためです。
確定拠出年金を取り扱っている運用管理機関(金融機関等)や国民年金基金連合会などに直接問い合わせてみる方法のほか、特定非営利活動法人「確定拠出年金教育協会」が運営しているサイト「個人型確定拠出年金ナビ 加入資格かんたん診断」を利用すると、加入資格があるか簡単に無料で調べることができます。
診断の結果、今は加入できなくとも法改正後(平成29年1月1日以後)に加入できる場合もあるので、この点はあらかじめ留意しておくようにしましょう。
6-2.運営管理機関を選びましょう
確定拠出年金の加入資格があることが分かったら、運営管理機関(金融機関等)を選びます。運営管理機関選びは、将来受け取る確定拠出年金額に大きな影響を及ぼすことになるため、慎重かつ重要であることは言うまでもありません。
筆者としてオススメしたいのは、「口座管理手数料が無料」という圧倒的コストパフォーマンスの松井証券です。
私もここの証券会社で確定拠出年金を運用しており、コストの安さと商品数にはかなり満足しています。
6-3.種別によって手続きが異なる場合も
国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者までの種別によって、確定拠出年金の手続きが異なる場合があります。
特に、会社員や公務員などの第2号被保険者が新たに確定拠出年金に加入する場合は、勤務先に対して「確定拠出年金に加入する旨の申し出をする」必要があります。
この理由は、加入限度額を超えていないか確認するためと、勤務先が企業年金制度などについての情報を国民年金基金連合会に対して登録しなければならないといった理由があるためとされています。
なお、確定拠出年金に積み立てるお金は、給料から毎月天引きされる方法以外にも、口座からの自動引き落としなど自分の選択した方法で利用することができます。
6-4.確定拠出年金の加入手続き
確定拠出年金の加入における実際問題として、取り扱っている金融機関へ足を運んだ場合でも納得できる対応が得られない場合も多々あるようです。したがって、加入手続き前には一度、金融機関等へ電話を入れてから加入手続きが対応可能かどうかをあらかじめ確認しておいたほうが安心です。
ただし、確定拠出年金の加入手続きにおける現状と致しましては、インターネットや電話で資料を請求して、郵送での申込みを行うケースが多いようです。
そして、この申込みが完了すると口座が開設され、運営管理機関の運用商品を毎月、定期的に購入・積み立てていくといった流れになります。
7.確定拠出年金法の法律改正について
平成28年5月24日に国会で確定拠出年金法の法律の改正が成立したことを受けて、平成29年1月1日から新たな確定拠出年金法が施行されることになりました。
この法改正で大きく変わった点は、何と言っても従来は確定拠出年金に加入することができなかった公務員や専業主婦・主夫も確定拠出年金に加入できるようになったことです。
ここでは、平成28年12月31日までと平成29年1月1日からに分けて確定拠出年金個人型に加入できる対象者と金額について解説していきます。
7-1.まずは「種別判定で自分は「第何号被保険者」であるかを確認する
国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までの人が強制的に加入させられる年金制度ですが、職業や扶養状況によって種別が「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3つに分けられます。
確定拠出年金に加入する際におきましては、これらどの種別であるかによって加入できる金額が異なるため、自分が国民年金の第何号被保険者であるかをあらかじめ確認しておく必要があります。国民年金のそれぞれの種別内容は、以下の表の通りです。
国民年金の種別内容と判定方法
| 種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
|---|---|---|---|
| 職業 | 自営業 フリーランス 学生 無職等 |
会社員 公務員 ※契約社員等 |
専業主婦 専業主夫 (第2号被保険者に扶養されている「配偶者」) |
国民年金の種別判定方法
自分の国民年金の種別を判定するには、上の表にあてはめて自分がどこに該当するのか確認します。
この時、注意しなければならない点の1つ目は、契約社員等です。ここで言う契約社員等とは、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどを含みますが、給料から厚生年金保険料が天引きされている人を指しています。
第2号被保険者とは、正社員やパートといった待遇で判断するのではなく、「給料から厚生年金保険料が天引きされている人」である点に注意が必要です。まずは、自分が第2号被保険者であるかどうかを確認して下さい。
2つ目の注意点として気を付けなければならないことは、第3号被保険者であるかどうかの判定です。
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている「配偶者のみ」となります。
よって、専業主婦や専業主夫のみ該当することとなり、扶養している成人の子どもは、第1号被保険者となりますので注意が必要です。第3号被保険者であるかどうかを確認し、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない場合はすべての人が第1号被保険者となります。
7-2.確定拠出年金加入対象者と加入限度額の関係(法改正前)
平成28年12月31日までにおける確定拠出年金加入対象者と加入限度額の関係は以下の表の通りです。
| 職業 | 種別 | 企業年金 | 加入の可否 | 加入限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 自営業 | 第1号被保険者 | - | ○ | 月額68,000円 |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業年金 ない会社 |
○ | 月額23,000円 |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業年金 ある会社 |
× | - |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業型 確定拠出年金 |
× | - |
| 公務員 | 第2号被保険者 | - | × | - |
| 専業主婦(主夫) | 第3号被保険者 | - | × | - |
上記表から、確定拠出年金に加入することができるのは、自営業者などの「第1号被保険者」と企業年金がない会社に勤めている「第2号被保険者」であることが分かります。
企業年金がない会社とは、すべてではありませんが、「中小企業の会社」をイメージするとよいかもしれません。それ以外の人は、平成28年12月31日までは確定拠出年金に加入することができないことになります。
7-3.確定拠出年金加入対象者と加入限度額の関係(法改正後)
平成29年1月1日からの法改正における確定拠出年金加入対象者と加入限度額の関係は以下の表の通りです。
| 職業 | 種別 | 企業年金 | 加入の可否 | 加入限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 自営業 | 第1号被保険者 | - | ○ | 月額68,000円 |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業年金 ない会社 |
月額23,000円 | |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業年金 ある会社 |
月額12,000円 | |
| 会社員 | 第2号被保険者 | 企業型 確定拠出年金 |
月額20,000円 | |
| 公務員 | 第2号被保険者 | - | 月額12,000円 | |
| 専業主婦(主夫) | 第3号被保険者 | - | 月額23,000円 |
上記表を見ると一目瞭然ですが、法改正によってすべての種別で確定拠出年金に加入できることになっています。
ただし、ここであらかじめ注意しておかなくてはならないことがあるのですが、いくつかの条件によっては、確定拠出年金に加入することができません。
これは、法改正前にも言えることなのですが、特に自営業者などの第1号被保険者の人で「国民年金の未納の状態がある場合」や「国民年金の免除履歴がある場合」などは、確定拠出年金に加入することができないことになっています。
今後の法改正によってこの辺が変わればさらに多くの人が確定拠出年金に加入できることになります。確定拠出年金に加入したい思いがあったとしても「加入資格」が無ければ加入することはできませんので、まずは自分の加入資格があるかどうかを確認してみることをおすすめします。
8.確定拠出年金の受け取り方法
確定拠出年金の受け取りは、原則として60歳から認められておりますが、実際にどのように受け取るのかにつきましても多くの皆さんが気になる点であると思います。
8-1.確定拠出年金は自動的に振り込まれない
実は確定拠出年金は、60歳になったからといって自動的に振り込まれるものではありません。
今まで長期間積み立ててきた確定拠出年金を受け取るためには、「記録関連運営管理機関=JIS&T」へ「裁定請求」をしなければなりません。裁定請求とは、年金を受け取りますので確認して下さいといった請求手続きのことで、これを行うことで年金を受け取ることができます。
つまり逆に言えば、裁定請求をしなければ積み立ててきた確定拠出年金を受け取ることはできません。
なお、国民年金や厚生年金といった公的年金を受け取る場合におきましても裁定請求が必要になりますので、ここの部分だけは、必ず知って押さえておくようにして下さい。誤解を招かないように、確定拠出年金と公的年金の裁定請求の違いについて以下の表へまとめて紹介します。
確定拠出年金と公的年金の受け取りと違い
| 年金の種類 | 確定拠出年金 (企業型・個人型) |
公的年金 (国民年金・厚生年金等) |
|---|---|---|
| 裁定請求の要・不要 | 裁定請求はどちらも「必要」 | |
| 裁定請求をするところ | 記録関連運営管理機関 (JIS&T) |
日本年金機構 |
| 受取開始年齢 | 原則として60歳から | 原則として65歳から |
| 受取方法 | 一時金(一括払い) 年金(分割払い) 併用(一時金と年金) 上記3つから選択 |
年金(分割払い)のみ |
| 受取期間 | 一時金の場合はお金を1回ですべてもらって受取終了
年金の場合はあらかじめ確定した期間に分割でお金を受け取って終了(10年間・20年間など人によって異なる) |
終身(死亡するまで) |
8-2.確定拠出年金の受け取りで大切なこと
前述しましたように、確定拠出年金の受け取りで大切なことは、「裁定請求を絶対に忘れない」ことがまず挙げられます。せっかく積み立ててきたとしてもそのお金を受け取らなければ何も意味がありません。
これをもう少し掘り下げて考えますと、自分が確定拠出年金に加入していたとしても、その事実を家族が知らないことも大きな問題となります。この理由は、確定拠出年金の受取時効があるためです。
つまり、一定期間が経過するまでに裁定請求をしておかなければ、時効消滅となって今まで積み立てたお金が1円たりとも受け取れないといったとんでもない事態が起こり得るといったことになるのです。
ちなみにこれは、多くの皆さんが加入している生命保険にも言えることです。こちらは余談となりますが、生命保険にも保険金を受け取るまでの時効期間がありますので、それを過ぎてしまってからの保険金請求は、保険金支払いの対象外となってしまいます。
従って、家族に知らせないで生命保険に加入しているといった事態はできる限り避けておく必要があります。
確定拠出年金と生命保険金の受取時効
| 内容 | 確定拠出年金 | 生命保険 |
|---|---|---|
| 受取権利時効消滅年数 | 5年間または10年間 | 3年間 |
確定拠出年金の時効年数が5年間と10年間に分かれているのは、先に解説しました受取方法による違いがあるためです。
こちらは、民法の規定を基としているようですが、あくまでも「家族に加入していることを伝え、家族間で情報を共有しておく」ことが大切です。配偶者だけでなく、場合によっては成人を過ぎた子に対して伝えておく必要性もあると考えることができるのではないでしょうか。
8-3.確定拠出年金の受け取り金額を定期的に確認しましょう
確定拠出年金に加入すると、現在の運用結果がどのようになっているのかといった定期報告が毎年届きます。これを見ると現在、自分が損をしているのか得をしているのかが一目で分かるような仕組みになっています。
確定拠出年金は、長期間に渡る積み立てになりますので、仮に投資信託で少しくらい損をしているからといって運用方法をすぐに切り替えたりするのは、一番効率の悪いやり方です。長い目で見ながら、資産配分(アセットアロケーション)や投資配分を考えて調整(リバランス)するのも1つの方法だと思われます。
9.確定拠出年金から給付される3つのお金とは
確定拠出年金から給付されるお金は、原則として60歳から受け取ることのできる老後資金だけではありません。実は、私たちが毎月納めている公的年金とほぼ同じ条件の給付が受けられる仕組みとなっています。
具体的には、
① 年を重ねたことによって給付される「老齢給付」
② 障害を患ってしまったことによる「障害給付」
③ 死亡したことによって遺族に給付される「死亡給付」
の3つの給付があります。
それぞれの内容と公的年金から受け取れる年金との関係を以下の表にそれぞれ個別に紹介します。
9-1.老齢給付の内容
| 内容 | 確定拠出年金 | 公的年金 | |
|---|---|---|---|
| 企業型・個人型 | 国民年金 | 厚生年金 | |
| 老齢給付 | 老齢給付金 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
| 受取可能年齢 | 原則として60歳 | 原則として65歳 | |
| 受取方法 | 一時金(一括払い) 年金(分割払い) 併用(一時金と年金) 上記3つから選択 |
年金(分割払い)のみ | |
| 受取期間 | 一時金の場合はお金を1回ですべてもらって受取終了
年金の場合はあらかじめ確定した期間に分割でお金を受け取って終了(10年間・20年間など人によって異なる) |
終身(死亡するまで) | |
老齢給付は、先ほど解説した「確定拠出年金と公的年金の受け取りと違い」と同じ内容になっておりますが、重要なポイントは、老齢給付金、老齢基礎年金、老齢厚生年金の3つの年金をすべて受け取ることができる点にあります。
9-2.障害給付の内容
| 内容 | 確定拠出年金 | 公的年金 | |
|---|---|---|---|
| 企業型・個人型 | 国民年金 | 厚生年金 | |
| 障害給付 | 障害給付金 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
| 受取可能条件 | 病気や事故で高度障害になった場合 (ただし、加入履歴などさまざまな条件を満たしている必要がある) |
||
| 受取方法 | 一時金(一括払い) 年金(分割払い) 併用(一時金と年金) 上記3つから選択 |
年金(分割払い)のみ | |
| 受取期間 | 終身(死亡するまで) | ||
障害給付は、確定拠出年金の加入者や加入者であった60歳以降の人が、病気や事故などによって所定の高度障害になった場合に支給されるものです。
ここで言う「所定の高度障害」とは、障害基礎年金を受け取っている人や身体障碍者手帳を交付されている人を指します。
また、公的年金から支給される障害基礎年金や障害厚生年金につきましても、それぞれ支給されるための障害等級が異なっている特徴があります。
障害等級が「1級」や「2級」といった重度の状態の場合は、これら3つの障害給付をすべて受けることができますが、たとえば「3級」の場合ですと「障害厚生年金」のみ受けられるなど細かな受取可能要件があります。
仮に重度の障害を患ってしまった場合には、障害給付が公的年金だけでなく確定拠出年金からも受けられることも知っておくべきでしょう。
8-3.死亡給付の内容
| 内容 | 確定拠出年金 | 公的年金 | |
|---|---|---|---|
| 企業型・個人型 | 国民年金 | 厚生年金 | |
| 死亡給付 | 死亡一時金 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 受取可能条件 | 死亡した場合 (ただし、加入履歴など様々な条件を満たしている必要がある) |
||
| 受取方法 | 一時金(一括払い) | 原則として年金(分割払い) ただし条件によって死亡一時金もあり |
|
| 受取対象 | 死亡した人の遺族 | ||
死亡給付は、確定拠出年金の加入者や加入者であった60歳以降の人が、死亡した場合にその遺族に対して支給されるものです。
死亡給付も障害給付と同様に、お金を受け取るためには、加入履歴を含めた様々な条件を満たしている必要があります。また、死亡給付の大きな特徴として確定拠出年金の場合、死亡一時金といった一時金のみの取り扱いであることが挙げられます。
この死亡一時金は、遺族が受け取ることになりますが、お金を受け取るためには「裁定請求」を必ず行う必要があります。
また、死亡一時金の金額によりますが、この遺族に支払われる死亡一時金は原則として「相続税の課税対象」となります。
ただし、5年以内に先に解説した「裁定請求」を行うことで、相続税法で認められている「法定相続人の数×500万円」の非課税措置が受けられます。以下、法定相続人のイメージ図と解説を掲載していきます。
法定相続人のイメージ図
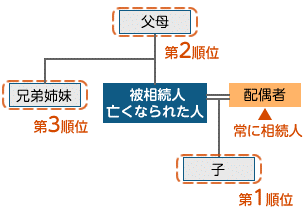
出典 政府広報オンラインより引用
法定相続人とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ人のことを言います。上記図における法定相続人とは、「配偶者」および「子」になります。子が2人いる場合は、配偶者と2人の子で法定相続人は3人といったようなイメージです。
仮に死亡した人の確定拠出年金における死亡一時金が1,000万円あった場合、法定相続人が2人以上いれば、受け取った1,000万円に対して税金を徴収されることはありません。
なお、こちらは余談となりますが、公的年金から支給される遺族基礎年金や遺族厚生年金につきましては、最初から税金が徴収されることはありません。
10.まとめ
本記事では、「初心者のための確定拠出年金 基本マニュアル」と題しまして、確定拠出年金の基本的な部分について幅広く、そして詳しく解説しました。
要点を改めて整理すると、以下になります。
【この記事の要点まとめ】
- 確定拠出年金の最大のメリットは「税金の節約をしながら、貯金や老後資金の蓄えを作れる」こと
- 運営管理機関には、商品数が多くて手数料の安い(口座管理手数料は無料)松井証券が圧倒的にオススメ
公式HP 松井証券での確定拠出年金を始める方はこちら - 確定拠出年金のデメリットは60歳まで引き出せないこと
- 確定拠出年金で得する鉄則は以下の3つ!
① 無理のない範囲で毎月の拠出金を決める。
② 手数料の安い運営管理機を選ぶ。
③ 早ければ早いほど得をする。思い立ったら小額からでもスタートしよう。 - 法律改正により、公務員や専業主婦も加入できるようになった。
時間を味方につける運用をして、確定拠出年金を始めてみよう。
確定拠出年金を利用した人と利用しなかった人では、将来において大きな差が生じることになると予測できます。多くの皆様が人生の充実とお金の有効活用のどちらも手にすることができることを祈りつつ、結びとさせていただきます。
PC用
関連記事
-
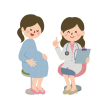
-
お仕事ママ必読!産休・育休中にもらえる3つのお金とは
産休・育休制度が使えることは知っていても、長期に渡って休むとなると、気になるのはやはりお金のことでは
-

-
受け取った生命保険金は相続税?贈与税?所得税?
多くの皆さんが終身保険や医療保険など、民間の生命保険会社が取り扱っている生命保険を契約して加入し
-

-
SOMPOケアネクストが見守りセンサー導入。IT化でサービス・安心感向上を狙う。
損保ジャパン日本興亜ホールディングスは、運営する有料老人ホームに見守りセンサーなどを導入し、サー
-

-
老後生活に資金はいくら必要?FPが教えるお金の準備マニュアル
あなたは老後の生活に不安を感じていますか? 生命保険文化センターが行った意識調査によると、この質問
-

-
妊娠~出産にかかる費用が安くなる公的保険と不妊治療助成制度をまとめました。
妊娠していることがわかると、大きな喜びを感じる一方で、今後のお金の面でさまざまな不安を抱えるようにな