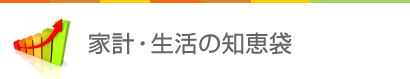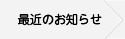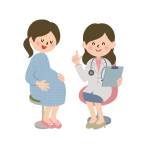「無痛分娩」のメリット・デメリット。出産費用や家計への影響とは?
公開日:
:
社会保障や公的保険
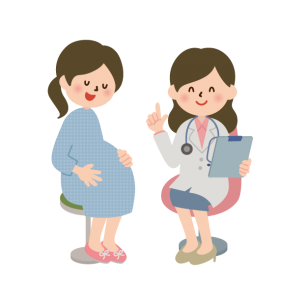
初めての出産に臨むときの大きな壁の一つが「出産の痛み」
どのくらい痛いの?
何時間くらいかかるの?
いくらインターネットで情報を得たとしても、経験のない痛みへの不安や恐怖心はなかなか消えないものです。
出産方法の選択肢の一つに「無痛分娩」があります。
海外では普及している「無痛分娩」ですが、最近では日本でも広がりを見せています。
今回は、これから出産する女性や今後出産する予定のある女性の皆さまに向けて、無痛分娩の内容やメリット・デメリットなどを幅広く紹介していきます。
そもそも無痛分娩とは?
無痛分娩とは、局所麻酔をすることで妊婦さんに対して出産の痛みをやわらげる効果がある出産方法のことをいいます。
無痛分娩には2つの方法があります。
1・出産を計画的に立てて行う「計画分娩」
2・陣痛が来るのを自然に待ち、出産時に麻酔を利用する分娩
必ず産院に事前確認を
無痛分娩は局部麻酔を使用するため、産科麻酔医の立ち合いが必要になります。
そのため、産科麻酔医が常駐している病院、または、産科麻酔医の勤務日でないと無痛分娩を利用することはできません。
分娩予約を検討している産院に、事前に無痛分娩が可能かどうか必ず確認しましょう。
無痛分娩の流れ
次に2つの方法の出産の流れについて紹介していきます。
「計画分娩」の場合
計画分娩の場合、一般的に前日から入院して準備が始まります。
【出産日の前日】
入院し、軽い麻酔を行った後、医療器具を使って子宮口を広げる
↓
【出産日当日】
陣痛促進剤という薬を使って陣痛を起こして出産
出産するまで痛みが強くなってきた場合は、麻酔薬を少しずつ追加して痛みを和らげていきます。
陣痛が来るのを自然に待つ場合
医師が診察によって予測したいわゆる”予定日“が近くなるまで、自宅で陣痛が来るのを待ちます。
陣痛が始まり間隔が10分程度に短くなってきてから病院へ行き、無痛分娩を行うための麻酔注入を始めていきます。
こちらも計画分娩と同じように出産するまで痛みが強くなってきた場合は、麻酔薬を少しずつ追加して痛みを和らげていきます。
無痛分娩のメリット
無痛分娩のメリットは、出産の痛みが少ないだけでなく、以下のようなメリットがあります。
・ 出産の痛みが少ないため、落ち着いて出産することができる
・ 出産がスムーズに進む
・ 出産後の体力の回復が早い
・ 急きょ、帝王切開などに術式が変更になった場合、迅速に対応が可能
・ 一部の産院では、出産が始まってからでも無痛分娩を選ぶことができる
出産が始まった後に無痛分娩にするかどうかを決めることができるのは、妊婦さんにとってはとても心強い仕組みです。
たとえば「出産の痛みに耐えられないから無痛にしたい」など、その場で判断できるようになっています。
前述したとおり無痛分娩に対応している病院である必要がありますので、事前にどのような出産方法が可能か病院に確認しておきましょう。
無痛分娩のデメリット
逆に無痛分娩のデメリットとしては、出産費が高額になってしまうことがあげられます。
具体的な出産費については後述しますが、ここでは無痛分娩のデメリットについて紹介していきます。
・ 出産費用が高額になる
・ 出産直後に頭痛や尿が自力で出しにくくなるといった副作用が生じる場合がある
・ 出産中に血圧が低下することがある
・ 出産の時間が長くなる可能性がある
・ 必ずしも無痛分娩ができるとは限らない
たとえば、椎間板ヘルニアで手術した経験のある人など一定の条件にあてはまっている場合、無痛分娩を受けられない場合もあります。
専門的なデメリットについては産科の先生とよく相談し、納得のうえでお産に臨みましょう。
出産費および無痛分娩費について
自然分娩・無痛分娩に関わらず、「出産費用」に不安を感じる方は少なくありません。
出産費用について確認していきましょう。
ポイント1・出産は公的保険の適用対象外である
そもそも「出産」は、厳密にいうと【病気】ではありません。
健康保険や国民健康保険などの公的保険の適用対象外となり、出産費や無痛分娩の費用についてはすべて自費での精算となります。
(出産育児一時金については後述します)
ポイント2・産院によって出産費用に差がある
出産は、出産する病院(産院)によって出産費が大きく異なる特徴があります。
おおむね「40万円~100万円」程度と、その金額も幅が広いものとなっています。
また、無痛分娩費は追加費用として10万円~20万円程度かかります。
無痛分娩を選択した場合の出産費用は、「50万円~120万円程度」と見積もっておくとよいでしょう。
出産費用についても、出産する予定の病院へあらかじめ確認しておきましょう。
ポイント3・出産育児一時金について
出産育児一時金とは、子どもを出産した場合に支給されるお金です。
支給元 健康保険や国民健康保険といった公的保険
支給される金額 「産んだ人数×42万円」(1人あたり42万円、2人で84万円など)
出産費用は保険適用外であることから、出産育児一時金は「出産にかかる費用を補うためのお金」と考えるのが自然です。
出産育児一時金を考慮したお金の計画を立ててみましょう
無痛分娩で出産する場合、先ほど費用例では「50万円から120万円程度」と紹介しました。
(無痛分娩費用50万円~120円)-(出産育児一時金 42万円)
=純粋に自己負担しなければならないお金 8万円~78万円
昨今では、出産に対応した生命保険なども販売されています。
貯蓄から出産費をまかなうのか、あるいは現在加入している生命保険で出産費をまかなうことができるのか、などについてもあらかじめ確認・検討しておきましょう。
まとめ
今回は「無痛分娩」という出産方法とメリット・デメリットについて紹介させていただきました。
諸外国では無痛分娩を利用した出産方法が全体的に多いものの、日本では分娩費用が高額になることや「痛く苦しい思いをして出産するのがあたりまえ」と固定概念が根深くあることで、大きく普及されていない現状があります。
無痛分娩は妊婦さんの出産にかかる痛みを和らげるだけでなく、安全性で優れている等のメリットがあります。
出産における不安や恐怖が拭い去れない時は、無痛分娩を選択する方法を視野に入れて、心も体もベストな状態で出産に臨みたいものです。
担当の医師や家族としっかりと相談をした上で、ご自身にとって最適な出産方法について選択をすることが大切なのはいうまでもありません。
本記事が、これからお母さんになられる皆さまのちょっとした気持ちの余裕が持ててもらえるようなきっかけになっていただければ幸いです。
PC用
関連記事
-

-
病気で働けなくなったらどうする?高額療養費制度と傷病手当金の申請から受給まで
今は健康に問題もなく働いているけれど、万が一大きな病気をして働けなくなったら? こんなことを考
-

-
「モラル」が問われる療養費問題
国民健康保険の療養費詐取の問題が大きくメディアで取り上げられました。このニュースが報道された事や発端
-

-
老後生活に資金はいくら必要?FPが教えるお金の準備マニュアル
あなたは老後の生活に不安を感じていますか? 生命保険文化センターが行った意識調査によると、この質問
-

-
医療費増加と今後の懸念
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2014年度の収支が前年度に比べて約2倍の3726億円の黒字になると
-

-
公的健康保険から支給される埋葬料・家族埋葬料とは
残念ながら人が亡くなる確率は100%です。いつかは訪れるこの時に備えて生命保険を掛け続けたり、貯蓄し